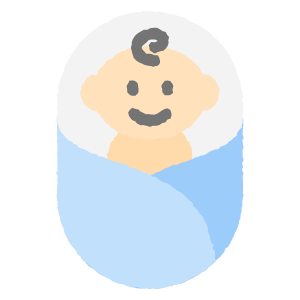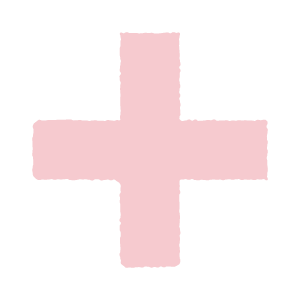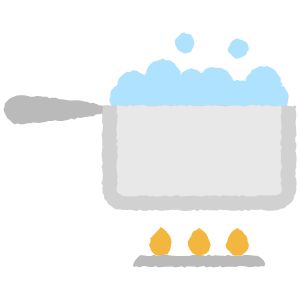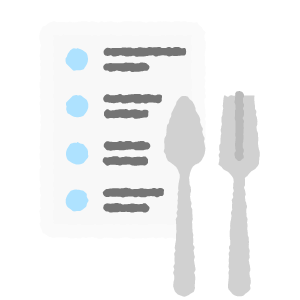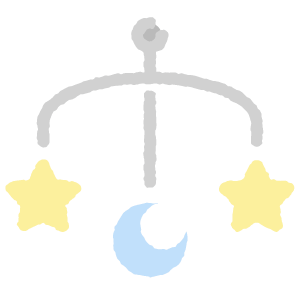新着の求人
-


☆看護師求人☆子どもが輝く環境をつくりませんか?
駅チカ4分♪手厚い配慮で子どもにしっかり寄り添えます。
-
月給:300,304 円 ~
-
看護師(正社員)
-
世田谷駅 徒歩4分
更新日:2025/07/03
-
-


看護師募集★新卒OK◎家賃補助・処遇改善手当あり♪固定勤務でプライベートも充実♪
地域に密着した保育を実践。家庭的な雰囲気の認可保育園です!
-
月給:242,400 円 ~ 247,500 円
-
看護師(正社員)
-
桜上水駅 徒歩9分
更新日:2025/07/01
-
-


事務員兼保育士急募!経験を広げられる保育園♪
地域に密着した保育を実践。家庭的な雰囲気の認可保育園です!
-
月給:206,200 円 ~ 215,800 円
-
保育士(正社員)
-
桜上水駅 徒歩16分
更新日:2025/07/01
-
エリアから探す
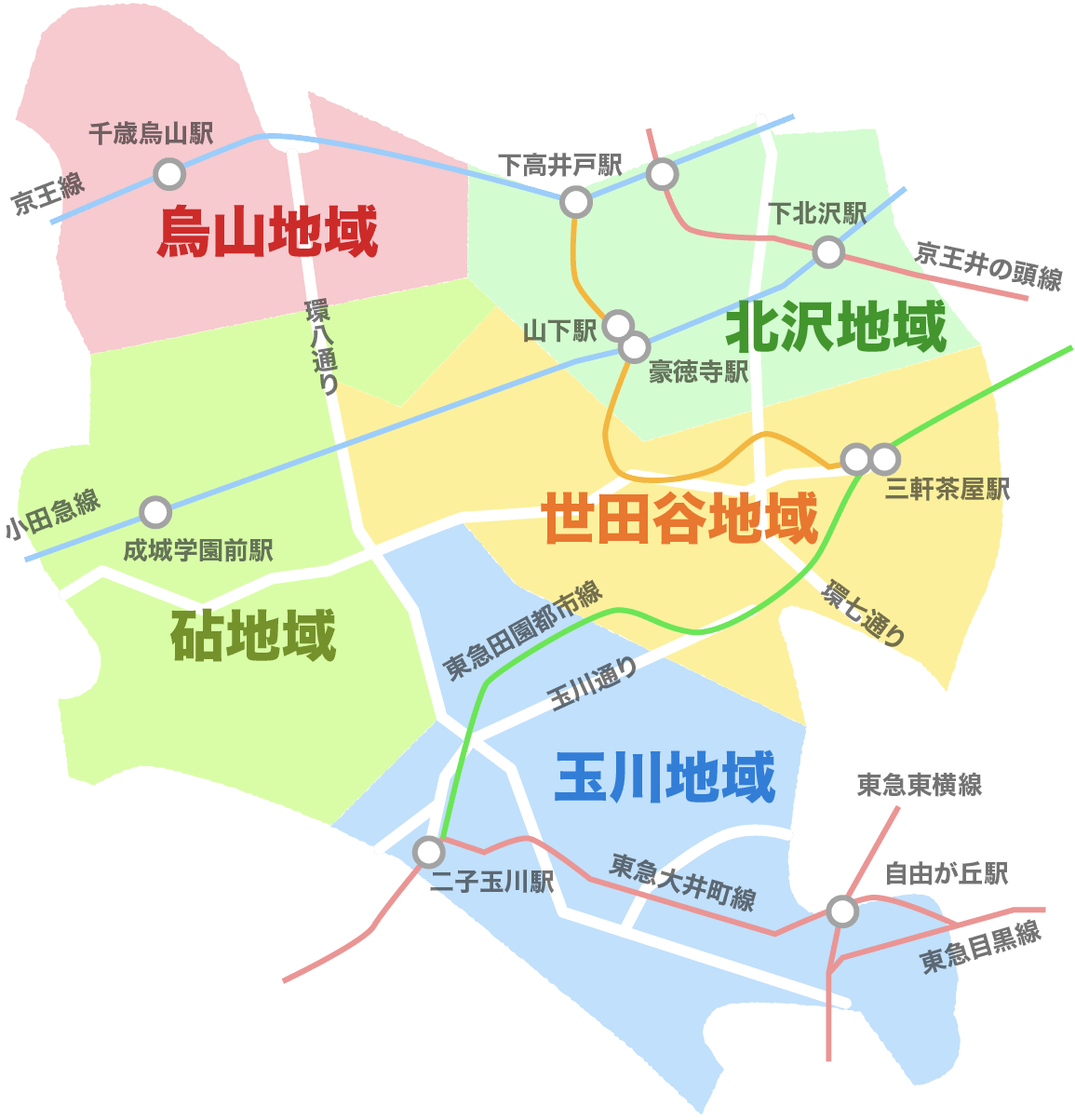
こだわり条件から探す
職種から探す
注目の求人
-


【二子玉川駅より徒歩7分】年間休日120日以上×残業少なめ!
完全週休2日制/持ち帰り業務なし/アート教育に取り組む保育園です☆
-
月給:215,000 円 ~ 360,000 円
-
保育士(正社員)
-
二子玉川駅 徒歩約7分
更新日:2024/11/29
-
-


週2日以上・1日4時間以上~OK☆平日のみ
平日のスキマ時間に働ける未経験OK求人です☆
-
時給:1,450 円 ~ 1,650 円
-
保育士(パート)
-
奥沢駅 徒歩6分 ※東急東横線「田園調布駅」徒歩8分
更新日:2023/09/12
-
-


研修充実!借上社宅あり◎
配置に余裕を持たせることで、一人ひとりに向き合う保育を行っています。
-
時給:1,300 円 ~ 1,500 円
-
保育士(パート)
-
三軒茶屋駅 徒歩15分 ※東横線祐天寺駅徒歩15分 ※渋谷駅より東急バスで下馬営業所前下車徒歩3分
更新日:2025/04/16
-
地域から探す
世田谷区の正社員求人
-


☆看護師求人☆子どもが輝く環境をつくりませんか?
駅チカ4分♪手厚い配慮で子どもにしっかり寄り添えます。
-
月給:300,304 円 ~
-
看護師(正社員)
-
世田谷駅 徒歩4分
更新日:2025/07/03
-
-


看護師募集★新卒OK◎家賃補助・処遇改善手当あり♪固定勤務でプライベートも充実♪
地域に密着した保育を実践。家庭的な雰囲気の認可保育園です!
-
月給:242,400 円 ~ 247,500 円
-
看護師(正社員)
-
桜上水駅 徒歩9分
更新日:2025/07/01
-
-


事務員兼保育士急募!経験を広げられる保育園♪
地域に密着した保育を実践。家庭的な雰囲気の認可保育園です!
-
月給:206,200 円 ~ 215,800 円
-
保育士(正社員)
-
桜上水駅 徒歩16分
更新日:2025/07/01
-
-

駅徒歩1分☆研修充実!借上社宅あり◎
配置に余裕を持たせることで、一人ひとりに向き合う保育を行っています。
-
月給:270,000 円 ~ 524,000 円
-
保育士(正社員)
-
桜新町駅 徒歩1分
更新日:2025/06/27
-
-

駅徒歩3分☆研修充実!借上社宅あり◎
配置に余裕を持たせることで、一人ひとりに向き合う保育を行っています。
-
月給:270,000 円 ~ 524,000 円
-
保育士(正社員)
-
下北沢駅 徒歩3分
更新日:2025/06/27
-
世田谷区の契約社員求人
-


☆契約社員求人☆働きやすい環境で働きませんか?
法人本部に業務改善担当者がおり、各園を回って職員の声を聞き、働きやすさのアップデートをしています!
-
月給:260,900 円 ~
-
保育士(契約社員)
-
下北沢駅 徒歩5分
更新日:2025/04/30
-
-


未経験からベテランまで歓迎!働きやすい環境での保育のお仕事です☆
勤務日相談可能☆京王線「上北沢駅」徒歩5分で通勤ラクラク♪
-
時給:1,250 円 ~
-
保育士(契約社員)
-
上北沢駅 徒歩5分
更新日:2025/02/19
-
-

少人数保育☆園長・主任候補募集
小規模園ならではの温かな保育環境づくりに挑戦しませんか?仕事とプライベートの両立◎
-
月給:280,000 円 ~
-
保育士(契約社員)
-
三軒茶屋駅 徒歩7分
更新日:2024/11/27
-
-

土日休み、手当充実、定着率◎
未経験OK!保育の質の向上に努める当園でスキルアップしませんか♪
-
月給:233,200 円 ~ 255,500 円
-
保育士(契約社員)
-
二子玉川駅 からバス10分「砧南中学校前」徒歩1分、または小田急小田原線 成城学園前駅からバス13分「砧南中学校前」徒歩1分
更新日:2023/11/08
-
-

安心して長く働ける環境が整っています!
大手グループの運営する保育園で、環境が整っています☆
-
月給:211,250 円 ~ 227,500 円
-
保育士(契約社員)
-
祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩10分
更新日:2023/07/14
-
世田谷区のパート求人
-


【夏期アルバイト募集】週2~5日、勤務時間相談OK♪
7月~9月までの期間限定で高時給になります!
-
時給:1,500 円 ~ 1,650 円
-
保育補助(パート)
-
尾山台駅 徒歩3分
更新日:2025/06/27
-
-


【週2~3日から可】早番・遅番専門!選択可能◎19名の小規模保育園☆
家庭的な雰囲気の中で、子どもの「やってみたい!」を大切にする保育園です。
-
時給:1,300 円 ~
-
保育士(パート)
-
松陰神社前駅 徒歩4分
更新日:2025/06/24
-
-

早番・遅番勤務可能な方の募集です。週3日~☆勤務日・時間相談OK
未経験や無資格の方も応募OK♪経験者は大歓迎!
-
時給:1,225 円 ~ 1,510 円
-
保育補助(パート)
-
祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分
更新日:2025/06/20
-
-

【パート保育士募集】週2~5日、勤務時間相談OK♪
クラス運営の補助などのお仕事です♪駅チカなので通勤らくらく♪
-
月給:1,200 円 ~
-
保育士(パート)
-
尾山台駅 徒歩3分
更新日:2025/06/11
-
世田谷区の保育士求人
-
 事務員兼保育士急募!経験を広げられる保育園♪
事務員兼保育士急募!経験を広げられる保育園♪-
月給:206,200 円 ~ 215,800 円
-
保育士(正社員)
-
桜上水駅 徒歩16分
-
-
 週2日~、4時間~勤務可♪
週2日~、4時間~勤務可♪-
時給:1,300 円 ~ 1,600 円
-
保育士(パート)
-
上野毛駅 徒歩9分
-
-
 駅徒歩1分☆研修充実!借上社宅あり◎
駅徒歩1分☆研修充実!借上社宅あり◎-
月給:270,000 円 ~ 524,000 円
-
保育士(正社員)
-
桜新町駅 徒歩1分
-
-
 駅徒歩3分☆研修充実!借上社宅あり◎
駅徒歩3分☆研修充実!借上社宅あり◎-
月給:270,000 円 ~ 524,000 円
-
保育士(正社員)
-
下北沢駅 徒歩3分
-
世田谷区の保育教諭求人
-
 【2025年4月採用】保育環境抜群の認定こども園です。
【2025年4月採用】保育環境抜群の認定こども園です。-
月給:195,000 円 ~
-
保育教諭(正社員)
-
三軒茶屋駅 徒歩7分またはバス停「昭和女子大」徒歩0分
-
-
 賞与初年度から4.55ヶ月分☆新卒OK!
賞与初年度から4.55ヶ月分☆新卒OK!-
月給:181,800 円 ~
-
保育教諭(正社員)
-
三軒茶屋駅 から徒歩12分
-
世田谷区の保育補助求人
-
 【夏期アルバイト募集】週2~5日、勤務時間相談OK♪
【夏期アルバイト募集】週2~5日、勤務時間相談OK♪-
時給:1,500 円 ~ 1,650 円
-
保育補助(パート)
-
尾山台駅 徒歩3分
-
-
 早番・遅番勤務可能な方の募集です。週3日~☆勤務日・時間相談OK
早番・遅番勤務可能な方の募集です。週3日~☆勤務日・時間相談OK-
時給:1,225 円 ~ 1,510 円
-
保育補助(パート)
-
祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分
-
-
 週3日以上・1日実働3時間~☆フルタイムパートも可♪
週3日以上・1日実働3時間~☆フルタイムパートも可♪-
月給:1,400 円 ~ 1,650 円
-
保育補助(パート)
-
千歳船橋駅 徒歩11分または東急バス「宇山」徒歩1分
-
-
 13~18時半夕方短時間勤務☆保育補助☆
13~18時半夕方短時間勤務☆保育補助☆-
時給:1,200 円 ~
-
保育補助(パート)
-
桜新町駅 徒歩6分
-
世田谷区の看護師求人
-
 ☆看護師求人☆子どもが輝く環境をつくりませんか?
☆看護師求人☆子どもが輝く環境をつくりませんか?-
月給:300,304 円 ~
-
看護師(正社員)
-
世田谷駅 徒歩4分
-
-
 看護師募集★新卒OK◎家賃補助・処遇改善手当あり♪固定勤務でプライベートも充実♪
看護師募集★新卒OK◎家賃補助・処遇改善手当あり♪固定勤務でプライベートも充実♪-
月給:242,400 円 ~ 247,500 円
-
看護師(正社員)
-
桜上水駅 徒歩9分
-
-
 【急募】駅徒歩3分☆未経験OK!
【急募】駅徒歩3分☆未経験OK!-
月給:300,000 円 ~
-
看護師(正社員)
-
下北沢駅 徒歩3分
-
-
 賞与4ヶ月!経験者歓迎☆
賞与4ヶ月!経験者歓迎☆-
月給:230,970 円 ~ 238,810 円
-
看護師(正社員)
-
九品仏駅 徒歩8分 ※尾山台駅 徒歩9分
-
世田谷区の調理師求人
-
 月120時間以上~◎無資格でも応募可♪
月120時間以上~◎無資格でも応募可♪-
時給:1,170 円 ~
-
調理師(パート)
-
松陰神社前駅 徒歩7分
-
-
 無資格でも応募OK☆パート調理師
無資格でも応募OK☆パート調理師-
時給:1,200 円 ~
-
調理師(パート)
-
下北沢駅 徒歩8分
-
-
 無資格でも応募OK☆パート調理師
無資格でも応募OK☆パート調理師-
時給:1,200 円 ~
-
調理師(パート)
-
下北沢駅 徒歩8分
-
-
 車通勤OK♪経験不問!未経験者も歓迎☆
車通勤OK♪経験不問!未経験者も歓迎☆-
月給:210,000 円 ~
-
調理師(契約社員)
-
成城学園前駅 徒歩15分
-
世田谷区の栄養士求人
-
 ☆栄養士パート求人☆食育等の保育補助の募集です
☆栄養士パート求人☆食育等の保育補助の募集です-
時給:1,600 円 ~
-
栄養士(パート)
-
千歳船橋駅 徒歩11分または東急バス「宇山」徒歩1分
-
-
 駅徒歩1分☆未経験OK!栄養士複数配置園◎
駅徒歩1分☆未経験OK!栄養士複数配置園◎-
月給:240,000 円 ~
-
栄養士(正社員)
-
桜新町駅 徒歩1分
-
-
 年間休日120日以上/キャリアアップ給あり☆
年間休日120日以上/キャリアアップ給あり☆-
月給:232,000 円 ~
-
栄養士(正社員)
-
千歳船橋駅 徒歩16分
-
-
 年間休日120日以上/キャリアアップ給あり☆
年間休日120日以上/キャリアアップ給あり☆-
月給:232,000 円 ~
-
栄養士(正社員)
-
梅ヶ丘駅 徒歩6分
-
世田谷区のその他求人
-
 送迎ドライバー募集☆週2日~OK
送迎ドライバー募集☆週2日~OK-
時給:1,200 円 ~
-
その他(パート)
-
上野毛駅 徒歩15分
-
-
 週2日以上、1日2時間~OK☆資格不問
週2日以上、1日2時間~OK☆資格不問-
時給:1,200 円 ~ 1,500 円
-
その他(パート)
-
用賀駅 からバスで約10分/東急バス・小田急バス「農大前」から徒歩3分
-
-
 平日4時間OK♪未経験歓迎◎
平日4時間OK♪未経験歓迎◎-
時給:1,215 円 ~
-
その他(パート)
-
祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩18分
-